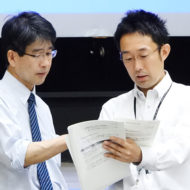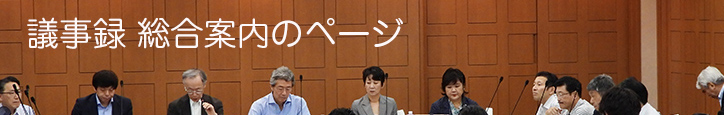日本医師会常任理事の松本吉郎氏は6月26日、次期薬価制度改革に向けて「薬価算定組織の意見」が示された中医協・薬価専門部会で、「評価すべき効能・効果の追加はあくまでも他の疾患領域への適用、いわゆるリポジショニングと呼ばれるものに限るようにお願いしたい」と求めた。【新井裕充】
「薬価算定の基準に関する意見」は5項目。このうち「イノベーションの評価」では、「優越性を示したもの」を評価する意向を示している。
新規収載時に新薬創出等加算の要件を満たさなかった医薬品について、収載後に追加された効能が、新規作用機序により既存治療に対して比較試験により優越性を示したもの (※) 等に該当する場合は、薬価改定時に新薬創出等加算の対象とすることにより評価することとしてはどうか。
※ 対象疾患に対する既存治療(本邦における治療方法として妥当性があるものに限る。)を対照群(プラセボ除く)に設定した臨床試験(当該承認を目的として実施されたもので、優越性を検証することを目的とした仮説に基づき実施された企業治験に限る。)を実施し、主要評価項目において既存治療に対する本剤の優越性が示されている場合。
松本氏は「効能・効果全体をイノベーションと呼ぶかどうかはさておき、効能・効果の追加は高額な抗体医薬品である抗がん剤でも行われてあり、また同じ領域の疾患名を追加することもまま起こっている」と指摘。その上で、「ここで評価すべき効能・効果の追加はあくまでも他の疾患領域への適用、いわゆるリポジショニングと呼ばれるものに限るようにお願いしたい」などと注文を付けた。
松本氏の発言は、以下のとおり。
[中村洋部会長(慶應義塾大大学院経営管理研究科教授)]
坪井委員長、どうもありがとうございました。
事務局のほうから何か補足があればお願いいたします。
では薬剤管理官、お願いします。
.
[厚労省保険局医療課・田宮憲一薬剤管理官]
特にございません。
.
[中村洋部会長(慶應義塾大大学院経営管理研究科教授)]
ありがとうございました。
それでは、ただいまの説明に関して、何かご質問、ご意見等ありましたらお願いいたします。
では松本委員、お願いいたします。
.
[松本吉郎委員(日本医師会常任理事)]
はい、まず薬価算定組織でのご検討に感謝を申し上げます。今後の議論ということになるとは認識しておりますけれども、この時点でいくつか、このご意見に対する考えを少し述べさせていただきたいと思います。
まず、(薬価算定の基準に関する意見の)1ページ目の2の「イノベーションの評価」の所でございますけれども、「新規作用機序により既存治療に対して比較試験により優越性を示したもの(※)」の所のアスタリスクの一番下の説明のところがございます。
※ 対象疾患に対する既存治療(本邦における治療方法として妥当性があるものに限る。)を対照群(プラセボ除く)に設定した臨床試験(当該承認を目的として実施されたもので、優越性を検証することを目的とした仮説に基づき実施された企業治験に限る。)を実施し、主要評価項目において既存治療に対する本剤の優越性が示されている場合。
この中に臨床試験が書いてありまして、「優越性を検証することを目的とした」というようなことでカッコ書きになっていますが、まずこの優越性を検証するので、この非劣性試験は含まれないという理解でよろしいのでしょうか、ということがまず1つと。
それから次に、臨床試験については、他の薬と比較する一種の営業目的の臨床試験ではなく、効果、効能・効果追認の可否判断に用いられる治験でよいでしょうか。ここでいう目的や主要評価項目につきましては、医薬品の直接的な患者への臨床的有効性について評価されるものと理解していますが、これもそれでよろしいということでしょうか。
まず、それをちょっとお聞きしたいと思います。
.
[坪井正博委員長(国立がん研究センター東病院呼吸器外科長)]
薬価の収載に当たっては、基本的には優越性試験を前提としていて非劣性試験は対象とされておりません。むしろ、市販後にですね、臨床科のほうの立場として実臨床においてどちらが有用性かということで非劣性のデザインというのが含まれることが多いかと思います。
.
[中村洋部会長(慶應義塾大大学院経営管理研究科教授)]
松本委員、それでよろしい?
.
[坪井正博委員長(国立がん研究センター東病院呼吸器外科長)]
加算については非劣性の判断は加わらないというふうに理解しています。
.
[中村洋部会長(慶應義塾大大学院経営管理研究科教授)]
では松本委員、お願いします。
.
[松本吉郎委員(日本医師会常任理事)]
はい。ちょっと続きまして、その薬価制度の枠組みにおいて評価が必要な比較試験があるのであれば、承認時あるいは承認後であっても、国が企業に指示して、市販後臨床試験を行うべきではないかというふうに思います。
効能・効果全体をイノベーションと呼ぶかどうかはさておいて、効能・効果の追加は高額な抗体医薬品である抗がん剤でも行われてあり、また同じ領域の疾患名を追加することもまま起こっております。
ここで評価すべき効能・効果の追加はあくまでも他の疾患領域への適用、いわゆるリポジショニングと呼ばれるものに限るようにお願いしたいというふうに思っています。
それから、この「(3)新薬創出等加算の品目要件」の所ですけれども、比較薬はリストとして示されていますが、中医協で議論するのではなく組織に委ねているところかと思います。
算定組織での比較薬の決め方を精緻に行うように、これは要望いたしますし、また加算適用品を比較薬とした場合であって、同等の有効性・安全性が認められて算定されたものについては有用性と革新性の程度がですね、加算適用品と同程度であるということかと思います。
つまり、プラセボには勝てても、加算適用品を対象薬とした治験で負けたら対象外でいいのではないかというふうに思います。
それから、最後ですけども、「(4)高齢者での高い有用性を示した薬剤に対する評価」の所ですが、対象患者として高齢者が想定されていたにもかかわらず、治験に組み入れてない試験デザインで承認を得た医薬品について、具体的にどの薬が該当するかは、これ、あえて聞きませんけれども、今後適切に治験を実施していただいた上で高い臨床的有用性が示された場合に加算を検討することは理解いたします。
日本医師会では、超高齢社会におけるかかりつけ医による適正処方を推進しております。製薬企業は効能・効果や有用性の宣伝だけではなくて、高齢者のデータがないことや、高齢者では危険な場合も含めて高齢者への適正処方に資する情報を提供するようにお願いしますし、また、データがないことについて添付文書に書いてそれで終わりということではないようにしていただきたいというふうにも要望いたします。以上でございます。
.
[中村洋部会長(慶應義塾大大学院経営管理研究科教授)]
ほか、いかがでしょうか。では有澤委員、お願いします。
.
[有澤賢二委員(日本薬剤師会常務理事))]
はい、ありがとうございます。
「イノベーションの評価」ということで全体的なコメントを出させていただきたいと思います。
特にですね、
(1)収載後の効能追加等による革新性・有用性の評価
(2)市販後に真の臨床的有用性が検証された既収載品の評価の拡充、あるいは
(3)新薬創出等加算等の品目要件
これらについての、当然、要件の精査というのは十分に検討もされなきゃいけないとは思いますが、基本的にイノベーションの評価を与えることには賛同させていただきたいと思います。
.
[中村洋部会長(慶應義塾大大学院経営管理研究科教授)]
では今村委員、お願いします。
.
[今村聡委員(日本医師会副会長)]
はい、ありがとうございます。
ちょっと、非常にプリミティブな質問で恐縮なんですけど、今の「真の臨床的な有用性」っていう言葉があるんですけど、基本的には有用性があってその薬として認められてる。
この「真の」って言っているのはどういう意味合いなんでしょうか、これ。
.
[中村洋部会長(慶應義塾大大学院経営管理研究科教授)]
これは・・・
では坪井委員長、お願いします。
.
[坪井正博委員長(国立がん研究センター東病院呼吸器外科長)]
 ケース・バイ・ケースかとは思うんですけど、実際には日本の患者さんばかりを対象にするものではないものもありますので、安全性の面を含めて、日本の患者さんでどうだったかというところで、もし前向きで検証されたような結果が出れば、それは真の有用性と思いますし、
ケース・バイ・ケースかとは思うんですけど、実際には日本の患者さんばかりを対象にするものではないものもありますので、安全性の面を含めて、日本の患者さんでどうだったかというところで、もし前向きで検証されたような結果が出れば、それは真の有用性と思いますし、
私が関わっているがんの領域においては、多くの場合は無再発生存とかって、全生存とは違うところで評価がされているので、生存率が本当に延長しているかどうかというところについては非常に大きなインパクト、患者さんにとっても医療にとっても大きなことだと思いますので、
そういった評価が出たときに、改めて「真の有用性」というふうな形で、今、議論をしていると思います。今後もそのつもりでおります。
.
[今村聡委員(日本医師会副会長)]
はい、ありがとうございます。
いろいろなケース・バイ・ケースというお話がありましたけれども、なかなか難しいとは思うんですけれども、真のものに対してはという、その言葉が使われているので、ある程度の定義というかですね、そういうものを専門的には先生方がちゃんと検討していただければありがたいなと。
で、もう1点。3(再生医療等製品への対応)の(1)の傾斜配分のお話があります。
近年、再生医療等製品であって著しく単価の高い品目が収載されている。収載時の補正加算額は加算前の価格に比例するため、これらの品目では、加算率が大きくない場合でも補正加算額は非常に大きくなる。
→ 著しく単価の高い再生医療等製品は、補正加算率を傾斜配分してはどうか。(一定の額より高ければ低い加算率にする。)
これについては私も賛成なんですけれども、前回ちょっとここでも申し上げた、非常に有用な再生医療等製品であっても、その薬の量が1つの剤形しかないために、ものすごく残薬が発生する、廃棄しなきゃいけない量のお薬がこう、たぶん出てくる可能性があって、
やはりそういったものっていうのは、ぜひそのメーカーにはそういうことも考えて、お薬作っていただきたいなということがあるので、少しそういった傾斜配分の検討もしていただければありがたいかなというふうには思っております。以上です。
(中略)
[松本吉郎委員(日本医師会常任理事)]
もう1点。最後の5ページ目の「その他」の所で長期収載品のことが出ておりますけれども。
1点質問なんですが、このG1に該当した医薬品って出てますけど、この該当した医薬品はどのくらいあったのでしょうか。また、今後のその見通しについても教えていただきたいというふうに思います。
.
[中村洋部会長(慶應義塾大大学院経営管理研究科教授)]
これは薬剤管理官、お願いします。
.
[厚労省保険局医療課・田宮憲一薬剤管理官]
はい。平成30年度改定におきましては、G1対象品目は38成分85品目。それから、後発品との価格差の関係でG1になったりG2になったり、Cになったりするのですが、G2の対象品目は137品目、293品目ということでございました。
で、今後の見通しということでございますけれども、いま申し上げたとおり、長期収載品と後発品との関係の中でですね、G1、G2、どちらの区分になるかとかいろいろございますし、
また、現時点ではちょっとどういう、どれくらいの成分があるかというのは手元では数字は持ち合わせておりませんので、また実際の薬価改定の際にはですね、どういう形になったかということはお示しさせていただければというふうには思っております。
(中略)
[平川則男委員(日本労働組合総連合会総合政策局長)]
ちょっと、私、まず順番として治験の在り方の問題のような気がいたしましたので、ちょっとそれは感想として言わせていただきます。
それから、あと最後、5ページの「その他」の意見の所で、医療環境が良くない場合には効果が相対的に大きく出るというふうなことのご意見がありましたけども、
(2)その他の意見
医薬品の有用性に関し、下記の意見が委員より出された。・ 医療環境が良くない場合には医薬品の効果が相対的に大きく出るなど、状況によって有用性の程度が高く見積もられることも考えられるので、実際の医療環境における有用性が検証できることが重要ではないか。
このへんも、今までもそういう薬があったというふうなことなのでしょうか。それであれば、ちょっと、優越性に関しての評価ということ自身がですね、問題として出される可能性があるかと思いますけれども、このへん、どういう議論があったのかをお聞きしたいと思います。
.
[中村洋部会長(慶應義塾大大学院経営管理研究科教授)]
これはどうですか、薬剤管理官のほうから? それとも。じゃあ、薬剤管理官、お願いします。
.
[厚労省保険局医療課・田宮憲一薬剤管理官]
薬価算定組織の中ではですね、具体的に何か個別にこういう事例があったということで議論があったわけではなくてですね、
どちらかというと強調されたのが、臨床試験成績を基にですね、有用性を評価しているわけですけれども、やはりその実臨床の中でですね、しっかりとその有用性、有効性とかが検証されるというようなものがやはり重要であるといった点からですね、そういう意見がありましたので、
今回、算定組織からのご意見の中にも、ご紹介、ご提案があったというものでございます。
.
[中村洋部会長(慶應義塾大大学院経営管理研究科教授)]
はい。平川委員、お願いします。
.
[平川則男委員(日本労働組合総連合会総合政策局長)]
要するに、具体的に個別の薬に関して、こういう問題があったということではないということですね。
.
[坪井正博委員長(国立がん研究センター東病院呼吸器外科長)]
はい。そのようにご理解いただいて結構だと思います。
.
[中村洋部会長(慶應義塾大大学院経営管理研究科教授)]
はい。では松本委員、お願いします。
.
[松本吉郎委員(日本医師会常任理事)]
今、治験の話が出ましたので、5ページ目の一番下の所に関わることかと思いますけれども、
確かに新薬承認のための治験は限られた環境で、まあ、環境や患者でできるだけ有効性を高く出すために、通常、さまざまな条件をいろいろ設定して行われるということになりますので、この算定組織の意見のご懸念は当然かとは思いますけれども、
しかし、効果が確認された治験並みの厳しい患者選択状況を見つけて承認するのかといえば、そうではなくて、患者さんの生活環境、まあ、いろいろな併存する疾患や併用薬など、治療に影響を与える要因は多々あります。
ただ、こうした要因を全て加味して治験するかというと、それも違っていて、あくまで患者さん1人ひとりが異なるので、罹患した患者さん全体として検証すべきような医薬品があるならば、承認条件として国が指示をすべきだというふうに思います。
結果に基づいた、その効能・効果の制限を設けるなど、薬価制度とはまた別の話にもなるのかなという感じもしますけれども、このへんは厚労省としてはどんなふうにお考えでしょうか。
.
[中村洋部会長(慶應義塾大大学院経営管理研究科教授)]
薬剤管理官ですか、薬剤管理官、お願いします。
.
[厚労省保険局医療課・田宮憲一薬剤管理官]
はい。ご指摘のとおりですね、承認時にですね、有効性を、さらなる有効性を検証するためにですね、承認条件ということで個別の試験を指示するようなこともございますので、
そこは承認審査の段階でですね、実際の個々の製品の承認時までのデータを踏まえてですね、必要な対応は行ってきているところだというふうには理解しています。
(後略)




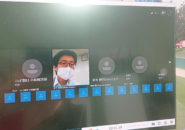





_20190925薬価専門部会-185x130.jpg)




【速記録】_ページ_01-のコピー.jpg)
【速記録】_ページ_01-のコピー.jpg)
【速記録】_ページ_01-のコピー.jpg)
_2023年8月2日の総会-1-190x190.jpg)

_2023年6月21日の中医協総会-190x190.jpg)








_2022年8月3日の中医協総会-190x190.jpg)















-190x190.jpg)


_20190807_中医協材料ヒアリング-300x300.jpg)