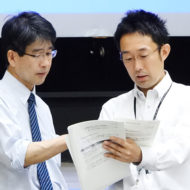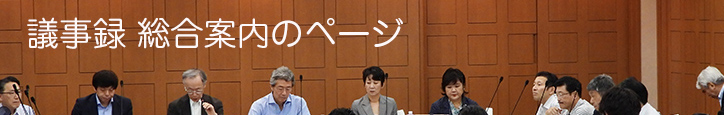6月8日の入院外来分科会に令和4年度の調査結果が示されました。【新井裕充】
厚労省担当者の説明は以下のとおり。なお、本稿では訂正後の資料を使用しています。P211以外にも訂正があるかもしれません。
〇尾形裕也分科会長(九州大学名誉教授)
ただいまより、令和5年度第2回「診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会」を開催いたします。
ご案内のとおり、5月8日から新型コロナウイルス感染症が類型変更されたことに伴い、本日の開催から久しぶりに対面を基本としつつ、オンラインも組み合わせての開催というふうにいたしております。
また、今回の会議の公開につきましては、YouTubeによるライブ配信で行うことといたしております。
はじめに委員の出欠状況について、ご報告いたします。本日は委員全員がご出席です。なお、田宮委員が早退予定というふうに伺っております。
それでは早速、議事に入らさせていただきます。まずは1つ目の議題でございます。「令和4年度調査結果(速報)の概要について」につきまして、まず事務局から資料の説明をお願いいたします。
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
〇厚労省保険局医療課・加藤琢真課長補佐
はい。事務局でございます。それでは、大部になりますけれども、「入-1」令和4年度の調査結果速報の概要をご説明させていただきたいと思います。
非常に大部でございますのでポイントのみ、かいつまんでご説明させていただきますことをご了承いただければと思います。
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
それでは、「1 調査の概要・回収の状況について」ということで、
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
3ページ目、4ページ目に、これまでもご案内させていただきました令和4年度の調査の概要をお示ししておりますが、
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
5ページ目にですね、回収状況ということで回収率をお示ししています。
これ前回もご報告しておりますけれども、こちら回収率、非常に重要なポイントでございますが、
コロナ禍ではございますが、これまでの例年と同等程度の回収率ということで、上がったところ下がったところございますが、同等程度の回収率だったというふうに受け止めております。
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
「2 調査結果」ということで、6ページ目以降。
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
まず「共通項目」ということで、8ページ目以降ですね、入院料ごとの基本的なデータを並べております。
特に今回は介護報酬との同時改定ということでもございますので、特に高齢者の認知症の状況、あるいはADLに関連するような項目を病棟ごとで少し分析しております。
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
8ページ目から平均在院日数。
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
そして、9ページ目は年齢の階級別の分布。
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
10ページ目以降、認知症や要介護度別の患者の割合や手術との兼ね合い、そういったところをお示ししております。
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
また、リハビリテーションや栄養、最終段階の意思決定の支援について、各入院料ごとで、どの程度取り組まれているのかということで今回お示ししましたので、ご覧いただければと思います。
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
飛ばしていただきまして、24ページ目からが各入院料ごとの、まず分析になっていきます。
24ページ目以降、まず一般病棟の入院基本料等における「重症度、医療・看護必要度」の施設基準等の見直しの影響について(その1)ということで、ご説明させていただきたいと思いますが、
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
いずれの調査に関しましても冒頭、今回は26ページ目以降ですが、開設者、
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
あるいは、ほかの入院料の届出状況、いわゆるケアミックスの状況。
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
そして各病棟の平均の職員数などをそれぞれ並べております。
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
そして29ページ目は、コロナの受入状況ということで、どの程度、重点あるいは協力医療機関として指定を受け、取り組まれたのかということをお示ししておりますし、
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
30ページ目は、その病床の変更の意向などをまとめております。
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
34ページ目以降、平均在院日数、
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
在宅復帰率等をお示ししておりまして、
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
36ページ目は急性期充実体制加算。前回の改定で導入しておりますけれども、この実績の状況を届出のあるなし、を比べてお示ししておりますが、
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
際立ったところとして、全身麻酔、化学療法、そして救急自動車等の搬送の件数などが、この加算の届出がありのところが多いというような結果が鮮明に出てまいりました。
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
37ページ目。届け出ていない理由に関しましても、「手術等に係る実績」のところが400床以上のところで一番多い理由として挙がってきております。
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
また、40ページ目以降は必要度の届出状況。
Ⅰ・Ⅱということで、Ⅱが多くなってきているというな傾向と、
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
そして41ページ目。こちらは中医協での総会でもご議論いただきましたが、必要度に関する設問で、該当患者割合の比較をしております。
令和3年度に比べ令和4年度、一定程度、該当患者割合はいずれの入院料においても低くなっているというような傾向が見てとれております。
こういったところは今後、また届出の状況なども併せて分析していきたいというふうに思っております。
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
44ページ目以降、特定集中治療室の管理料の見直しの影響ということでおまとめしております。
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
最初に、改定説明資料を載せておりますが、48ページ目以降、届出病床数、平均在室日数をお示ししておりますが、
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
今回も50ページ目。SOFAスコアで患者の状態をお示ししています。
こちら、ICUの1・2に関しては、3・4に比べて一定程度、重症な患者さんが受け入れられているというような傾向が見てとれるかというふうに思っております。
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
51ページ目、52ページ目は、必要度の結果になっておりますし、
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
54ページ目に飛ばせていただきますと、前回改定で導入した「重症患者初期支援加算」の届出の状況で、
こちら、メディエーターとして配置されてるのは看護師、社会福祉士が一番多いというような結果と。
そして、そのメディエーターが介入している患者数がですね、右上でございますが、10名程度であるというようなことは今回示されております。
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
56ページ目になりまして、重症患者対応体制強化加算。
こちらも新規導入されておりますけれども、現在、届出の数としましては調査ベースですと9施設ということで、割合としてはいくらか低い状況でございますが、
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
届出が困難な理由としては、「看護師2名以上を確保できない」あるいは、急性期充実体制加算が届け出られないといったところが挙がってきております。
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
58ページ目。早期離床・リハビリテーション加算。
ICU以外、届け出れることになりましたが、右側をご覧いただきますと、今現状、まだかなりばらつきがございますが、一定程度のところが取り組んでいるというようなことが見てとれます。
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
60ページ目以降、まず(3)地ケアと回リハの要件の見直しの影響ということでお示ししております。
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
最初、改定説明資料が並んでおりますけれども、
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
65ページ目に病床種別のですね、許可病床数ということでお示ししておりまして、
nはいくらか低い、少ないわけではございますが、療養病床を地ケアとして活用しているところは200床以上の医療機関が多いというような傾向が見てとれます。
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
66ページ目以降、こちらもケアミックスの状況等をお示ししておりますし、
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
68ページに、地ケアでの新型コロナ感染症の受け入れ状況等もお示ししております。
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
69ページ目以降、前回の改定の中で、地ケアの1つの改定の目玉でもございましたが、救急を受け入れられているかどうかということで、
救急告示、あるいは救急医療の体制について全般的なところを69ページ目に、その状況をお示ししておりまして、
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
70ページ目に、実際にどれぐらい受けられているのかということでお示ししています。
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
右側のグラフを見ていただきますと、0から100というようなところも多くございますが、
一方で1,000以上というような医療機関もあって、こちら当然、今後、ほかの病床、病棟をどういったものを持っているのかといったところも含めて検討が必要というふうに認識しております。
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
72ページ目以降はですね、地ケアにおける在宅医療の状況ということでお示ししております。
72ページ目左側。地ケアの1に関しては、95%は在宅医療の提供を実施しているというような状況でございます。
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
そして、実績要件に関しまして、73ページ目、74ページ目にお示ししておりますが、
今現状では、満たしているものに関しては、①の在宅患者訪問診療料の算定が一番満たしているものとしては多いというような傾向でございます。
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
75ページ目に訪問看護ステーションの併設の状況。
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
そして、76ページ目に入棟元別のですね、分析をお示ししています。
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
77ページ、78ページ目は、緊急患者の受入れの数、在宅復帰率等をお示ししておりますし、
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
80ページ目は、平均在院日数の分布をお示ししています。
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
83ページ目以降、回リハの分析になります。
最初、改定説明資料が並びますが、
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
こちら、前回の改定の中でも大きく触れました。90ページ目にございます。いわゆる「心リハ」でございます。
現在の届出の意向。そして届出を行えない理由に関しましては循環器の医師の確保が困難など、医師の要件が主に挙がっております。
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
92ページ目は、重症度の割合。こちら変更しておりますが、それに対応するかたちで今現状、重症度の割合が以前よりも上がっているというような傾向が見てとれるかというふうに思います。
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
93ページ目は実績指数。こちらも変更を加えておりますが、それに対応するかたちで今の分布をお示ししています。
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
このようなかたちで回リハの前回の改定に伴った現状を今回お示ししています。
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
100ページ目以降、まず(4)で療養病棟の入院基本料ということで、改定した部分を中心にご説明させていただきたいというふうに思います。
103ページ目まで改定説明資料でございますが、
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
104ページ目。この開設主体。
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
そして、届出病床数。
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
職員の数ということでお示ししております。
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
107ページ目は、コロナの感染症の対応状況。
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
108ページ目は救急医療体制ということで、お示ししています。
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
110ページ目。医療区分2・3の該当割合ということで、今回、1と2と、そして経過措置対象病床ということでお示ししております。
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
療養病棟に関しましては、前回の改定のポイントとなるのは120ページ目になりますが、
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
中心静脈栄養を実施している患者に対する摂食機能、あるいは嚥下機能の回復に必要な体制がどれぐらい取られているかということで、
今回の結果からは、61%というところが体制があるというふうな回答でございました。
32%の中でですね、やはり嚥下機能検査、あるいは嚥下造影が実施する体制がないというようなことが主な理由として挙がってきております。
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
124ページ目以降、障害者施設等の入院基本料ということでおまとめしております。
これまで同様に届出病床、あるいは平均職員数をお示ししております。
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
129ページに病床利用率。
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
平均在院日数は130ページ目ということでお示ししています。
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
138ページ目以降は緩和ケア病棟の入院基本料。
こちらも同様に、開設者別、許可病床別、平均在院日数、在宅復帰率等をお示ししています。
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
146ページ目に、前回の改定で少し触れました疼痛の評価に関しまして、その傾向。
緩和ケア病棟入院料の1と2ということで比較してお示ししています。
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
148ページ目は、これまで例年どおり見ておりますが、平均待機期間ということで、
その施設基準が14日以内ということで、こちら多くの医療機関がそれを満たしているということをお示ししています。
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
150ページ目以降、新興感染症に対応できる医療提供体制の構築に向けた評価ということで、
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
主には感染対策向上加算の届出状況等と、実際に実施している取組について分析しています。
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
152ページ目がその届出状況でございまして、急性期入院料の1、あるいは2~3、4~6ということで、
加算の1から2・3ということで、その分布をお示ししています。
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
153ページ目は、実際に新型コロナ患者の受け入れの状況で、多くの加算の1、あるいは2の医療機関が受け入れてきているというような傾向が見てとれます。
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
154ページ目は、届出とその連携の状況ということで、連携している医療機関数。
加算1に関しては、連携施設、平均すると9ということになっておりますし、
サーベイランスへの参加状況も一定程度、良いというような結果が見てとれるのではないかというふうに思っております。
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
155ページ目は、これは同時改定の懇談会でもご議論いただいておりますけれども、高齢者施設に対する助言。
こちら一定程度、感染対策向上加算1において、もう既に実施しているという医療機関が6割を超えているというような状況が今回の結果から見てとれております。
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
また、156ページ目は、届け出ていない医療機関における感染対策の状況ということで、157ページ目までお示ししております。
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
158ページ目は、外来感染対策向上加算の届出の状況になります。
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
続きまして、159ページ目からが働き方改革に関連する評価になります。
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
こちら、161ページ目以降が実態調査。医師票の回答者の属性をお示ししています。
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
162ページ目に勤務状況の改善の必要性。
それ以降が診療科別、職位別に見た傾向をお示ししています。
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
166ページ目に医師の負担軽減策の実施状況ということで、実際に取り組まれているものをお示ししておりますが、
上5つの中に、実に3つの取組が薬剤師と関連した取組ということで、非常に連携して取り組まれている状況が今回見てとれたのかというふうに思っています。
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
ただ、167ページ目、施設基準の届出種別で見ますと、特定機能病院と、あるいは急性期一般入院基本料、地域医療体制確保加算届出の医療施設において、
その取組の状況においては、かなり差があるのではないかというような結果が出てきているというふうに思います。
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
168ページ目はICTの活用に関して。
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
169ページ目以降は、地域医療体制確保加算における分析をお示ししております。
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
172ページ目は医師事務作業補助体制加算に関連したもので、
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
174ページ目に、今回導入してます人事考課、あるいは、その院内教育に関して、実施状況についてお聞きしております。
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
175ページ目以降は看護職員の負担軽減・処遇改善に関する取組の状況をお示ししております。
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
また、179ページ目以降は病棟薬剤業務の実施加算1の届出や、周術期薬剤管理加算の届出の状況をお示ししています。
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
ここまでが働き方改革になりますが、181ページ目以降は外来医療に係る評価ということでお聞きしております。
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
184ページ目は「各種研修を修了した医師の有無」ということで、かかりつけ、昨今注目されておりますが、その研修を受けている医師の割合をお示しするとともに、
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
185ページ目は、時間外対応加算の種類ということで、時間外対応加算3の施設は比較的少ない傾向にあるというようなことが見てとれるかというふうに思います。
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
186ページ目以降、地域包括診療料・加算の届出状況と、
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
届け出ていない理由に関して、187ページ目、188ページ目でお示ししています。
やはり常勤の2名以上の医師が確保できない、あるいは、そういった常勤の医師や、在支診、時間外対応加算が届け出ていない、できないというようなことが最大の理由として、いずれの診療料と加算のほう、いずれも挙がってきているというような状況でございます。
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
189ページ目に関しては、今回届出を行った理由ということで、多かったのが、診療所に係る要件を満たすことができたと。
在支診になった、あるいは時間外対応加算1を新たに届け出たというようなところが項目として挙がってきているということになります。
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
また、要件を見直しました地域包括診療料の疾患に関連するものに関しては、192ページ目に今回、疾病別の患者数ということでおまとめしております。
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
194ページ目は、生活習慣病管理料の算定について困難を感じるところ。
その後、薬物療法に関連するものや眼科受診に関してお示ししています。
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
198ページ目は、紹介・逆紹介割合ということで、実際の今の割合に関して満たしている、満たしていないところの医療機関の分布をお示ししています。
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
199ページ目以降がオンライン診療。いわゆる情報通信機器を用いた診療、初診料の届出の状況ということで、
「届け出ている」という医療機関が31.9%に上るというような結果になってきています。
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
その診療実績等をお示ししておりますが、前回改定でも対応しました管理料に関しましては201ページ目。
特定疾患療養管理料のところが一番多いというような傾向が見てとれています。
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
202ページ目以降、届出の意向や行わない理由等をまとめております。
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
207ページ目以降がですね、患者調査ということで、実際の受診歴の有無。
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
そして所在地。実際に医療機関と患者の所在地が異なる所在地であったというようなところは5件ということで挙がってきております。
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
受けた方の患者調査において、受けた方の状況。今後、受けたいか。オンライン診療を受けたいか受けたくないかというところを、209ページ目以降、おまとめしておりますが、
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
▼ P211に重大な訂正あり。6月8日午後10時半ごろ、厚労省広報室より報道関係者に次のようなメールが送信された。オンライン診療を受けたいかどうかの設問について、「そう思う」「そう思わない」の回答が逆になっていた。同日の分科会で疑問の声が上がっていた。
報道関係者 各位
夜分に申し訳ございません。厚生労働省広報室報道係です。
標記について一部資料の修正がございましたので、以下のとおりお送りいたします。
修正箇所は「入─1 令和4年度調査結果(速報)概要」における、P211「対面診療/オンライン診療の受診希望状況(患者調査)」となります。
下段のグラフについて改めてデータを確認したところ、「そう思う」と「そう思わない」の数値が入れ違っておりました。この点修正しホームページに以下のリンクのとおり修正をしております。この度は会議後の資料修正となり大変申し訳ございません。
.
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
212ページ目以降、インターネット調査。これ、同様の質問を2,000人の方にお聞きしております。
回答者の3.3%がオンライン診療の受診歴がございまして、その内訳をそれ以降で分析しているということで、
一定程度の患者調査とインターネット調査、回答の結果に違いがあったというような結果になっております。
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
217ページ目以降、外来の化学療法ということで今回導入しておりますので、その届出の状況等をお示ししています。
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
221ページ目以降、職員の配置状況や指針の策定の状況。
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
患者に選択肢を提示できているか、というようなところをお示しするとともに、
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
一番、届出においてハードルとなっています時間外の対応の体制に関しては、225ページ目にお示ししています。
どのような体制で対応しているのかというようなところに関しては、電話またはメールにおける相談を常時受けられる体制を取っているというようなところや、
速やかに受診が必要な場合には自院において診療ができる体制を取っているというようなところが比較的、施設票(A票)においては多いというような結果が出てきています。
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
やはり時間外対応の体制に関して、非常にそれが整えられないことによって届出できないというような結果に関しては、227ページ目以降、お示ししています。
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
最後、230ページ目以降、「その他の調査結果」ということで、入退院支援加算の現状の届出状況。
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
届け出られない理由。
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
そして、239ページ目以降が認知症ケア加算に関しまして、現在、各医療機関における取組状況。
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
243ページ目に、身体的拘束を予防・最小化するための医療機関の取組の状況に関して、病棟種別ごとでお示ししているとともに、
具体的な取組内容を244ページ目にお示ししています。
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
そして、245ページ目は拘束の実施状況ということで、病棟種別ごとで、具体的に身体拘束をどれぐらい実施されているのかということをお示ししています。
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
最後、246ページ目。いわゆる「小児入管」の概要をお示しするともに、
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
_2023年6月8日の入院外来分科会.jpg)
実績のデータと、そして前回改定で対応しました時間外受入体制強化加算1・2の現在の届出状況を249ページ目にお示ししています。
非常に長くなってしまって大変恐縮ですけども、説明は以上になります。
〇尾形裕也分科会長(九州大学名誉教授)
はい、どうもありがとうございました。
ただいまご説明いただいた資料は令和4年度調査結果の速報ということでございますが、委員の皆さまには、この速報を踏まえ、今後、特にどのような観点から、さらに分析や検討等を進めていくべきかということについて、ご意見を承ればというふうに思います。
それではページ数もかなり多いので、3つのセクションに分けてご質問、ご意見をお願いしたいと思います。
まずは最初の1番目の共通項目。それから、2番目の調査結果のうち(1)の一般病棟入院基本料および(2)の特定集中治療室管理料等まで。
つまり、ページ数で言いますと、1ページから59ページまでの部分につきまして、ご質問、ご意見等を承りたいと思います。いかがでしょうか。はい。山本委員、どうぞ。
(後略)
.






の入院外来分科会-185x130.jpg)




【速記録】_ページ_01-のコピー.jpg)
【速記録】_ページ_01-のコピー.jpg)
【速記録】_ページ_01-のコピー.jpg)
_2023年8月2日の総会-1-190x190.jpg)

_2023年6月21日の中医協総会-190x190.jpg)








_2022年8月3日の中医協総会-190x190.jpg)















-190x190.jpg)


_20190807_中医協材料ヒアリング-300x300.jpg)