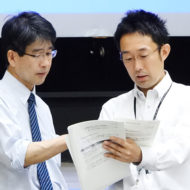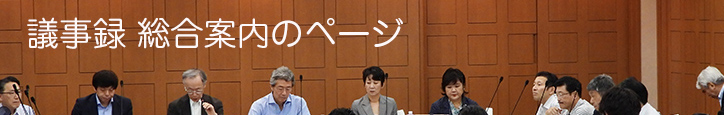厚生労働省の「医薬品の迅速・安定供給実現に向けた総合対策に関する有識者検討会」の議論が、大詰めを迎えている。過去に厚労省がつくった制度の機能不全を自ら認めるかのような話もあれば、厚労省が認めるのは難しいと目される指摘も有識者から出ている。果たして、厚労省が過去の“失敗”をどこまで認めるか。【本根優】
有識者検討会は当初よりやや遅れる格好で、5月中にも報告書をまとめる予定だ。直近の最大の課題は、後発品の安定供給と言える。
4月4日の会合では、厚労省が提示した資料の中で、後発品薬価の「3価格帯ルール」について、否定的な見解を示した。
「市場実勢価格加重平均値調整幅方式に基づき算定された薬価から、さらに価格帯集約により薬価が変動するため、製薬企業にとって予見性の乏しい制度になっている」
「適正な価格で販売している企業にとっては薬価が下がり、安売りした企業にとってはより高い薬価となるため、不公平な制度となっている」
後発品の3価格帯ルールは14年度薬価制度改革で、「価格のバラつき」が問題視され、設定されたものだ。しかし、10年近くが経過し、制度にネガティブな記述を堂々と盛り込んでいる。
一方で、厚労省OBの香取照幸構成員(兵庫県立大学大学院特任教授)は、総薬剤費とGDP(国内総生産)比率といった議論に総医療費の観点が抜けていると指摘しつつ「医療費はGDPの伸びを上回っている。省内で調整をした上で、薬価を財源捻出の調整弁とすることをやめてもらいたいと書き、それを言ったうえでやるべきことを書くべき」と持論を展開した。別の構成員からも同調する意見が出た。
ただ「薬価を財源捻出の調整弁としてきた」というのは、事実上そうだとしても、香取氏がやや憚りつつ発言したように、厚労省がそのまま認めることは困難な内容だろう。
香取氏の意見に対する、遠藤久夫座長(学習院大学教授)のコメントからも、そのあたりはうかがえる。
「議事録にはすべて残りますので」
.






-185x130.jpg)










【速記録】_ページ_01-のコピー.jpg)
【速記録】_ページ_01-のコピー.jpg)
【速記録】_ページ_01-のコピー.jpg)
_2023年8月2日の総会-1-190x190.jpg)

_2023年6月21日の中医協総会-190x190.jpg)








_2022年8月3日の中医協総会-190x190.jpg)















-190x190.jpg)


_20190807_中医協材料ヒアリング-300x300.jpg)