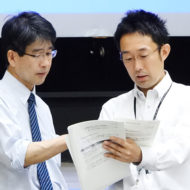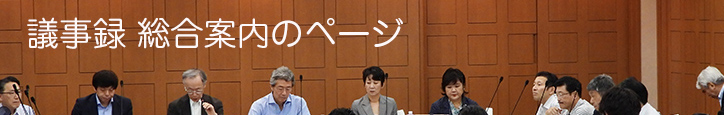医療福祉分野への労働力シフトには異論がある。財務省関係者は「日本全体で現役世代が減っていく中で、医療福祉に労働力が集中していいのだろうか。広い意味で大きな課題だ」と問題提起する。【鯉渕甫】
この意見に対して、医療福祉関係者は「財務省関係者の意見だから…」と看過したいだろうが、自陣営の厚労省関係者からも同様の“私見”が漏れてくる。
「人材の社会的適正配置の観点から、スキルの伸びしろが大きい20代の人材は福祉分野ではなく、GDP拡大に寄与する業種に就業する環境を整えたほうがよいと思う」
こうした見方は省庁だけでなく、意外にも、人材不足に瀕する当事者の業界関係者も口にする。社会福祉法人理事は「人材不足で2040年に事業を継続できているかどうか分からない」と懸念しながらも、自業界本位でない視点を持っている。
「2040年には医療と介護の従事者が他の職種よりも多くなるだろうという予測もあるが、もしその通りになったら、いびつな社会になってしまう。GDPに貢献しない業種の従事者が最も多くなる社会はいびつだ」
医療福祉人材の確保問題には、表立って発言しにくいホンネが潜んでいる。
そもそも国内の就業者全体のなかで、医療福祉分野の就業者数はどんな分布状況にあるのだろうか。
さる1月31日、総務省統計局は「労働力調査(基本集計)2022年」を発表した。22年平均の就業者数は6723万人。前年比で10万人増加した。最も増加した産業は「医療、福祉」で17万人増加し、情報通信業の14万人増加を3万人上回った。
産業別就業者数を見ると「医療、福祉」は908万人。「製造業」(1044万人)、「卸売業・小売業」(1044万人)に次いで就業者数が多かった。全就業者の7人に1人が「医療、福祉」で働いている計算だ。
18年に発表された「2040年を見据えた社会保障の将来見通し」(内閣官房・内閣府・財務省・厚生労働省)は医療福祉分野の就業者数は2040年度1065~1068万人と試算。就業者数全体の18.8~18.9%を占め、5人に1人が医療福祉分野で働いていることになるが、あくまで希望的観測にすぎない。
現に22年版厚生労働白書によると、40年に96万人が不足するという。この窮状は医師の働き方改革の足を引っ張りかねない。「勤務医の時間外労働の年間上限は原則960時間」などを盛り込んだ改正医療法の施行は24年4月。あと1年に迫っている。
医師の働き方改革の大前提はタスクシフトだが、シフトするタスクの担い手になる人材確保が焦眉の急だ。病院団体関係者は「タスクシフトを進めるには医師以外の人材が必要。他の産業に打ち勝って人材を確保していくことが病院経営の課題になるだろう」と述べる。
だが、人材不足が深刻なのは医療福祉業界だけではない。例えば経済産業省の試算によると、IT人材は30年に最大で79万人不足する。防災に備えて重要インフラ工事が増加する建設業界では、技能労働者が25年に最大で93万人不足すると国土交通省が試算している。
これら他業界と競い合って、かりに病院団体関係者が述べた「他の産業に打ち勝って人材を確保していくこと」がかなっても、40年に就業者の5人に1人が医療福祉分野で働けば、5人に1人の給料は社会保障費で賄われる事態になる。
それだけの労働力が社会保険事業という計画経済のもとで働くことは、さすがに想定できない。
.

















【速記録】_ページ_01-のコピー.jpg)
【速記録】_ページ_01-のコピー.jpg)
【速記録】_ページ_01-のコピー.jpg)
_2023年8月2日の総会-1-190x190.jpg)

_2023年6月21日の中医協総会-190x190.jpg)








_2022年8月3日の中医協総会-190x190.jpg)















-190x190.jpg)


_20190807_中医協材料ヒアリング-300x300.jpg)