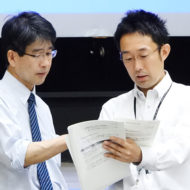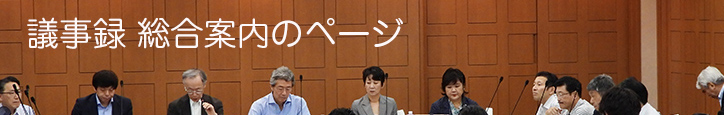9月14日の中央社会保険医療協議会総会で、城守国斗委員(日本医師会常任理事)は退任の挨拶を行い、「安易に(中医協の)守備範囲を狭めてはいけない」と、中医協“軽視”の風潮を戒めた。【本根優】
さらに、城守氏は「診療報酬上の制度設計については、専門職が委員を務める中医協の場において、主体的に議論し決定すべきだ」とも語った。
そうした思いは診療側、支払側に共通している。11月9日の中医協・薬価専門部会では、厚生労働省の「医薬品の迅速・安定供給実現に向けた総合対策に関する有識者検討会」から、議論の状況について報告を受けた。
薬価専門部会では、23年度の中間年改定をどうするかが最優先課題。だが、医政局医薬産業振興・医療情報企画課の安藤公一課長は、委員からの質問に対し、有識者検討会として「23年度(の中間年)改定に向けた何らかの取りまとめは考えていない」と返答した。24年度の制度改革に向けた報告書を23年4月をメドにまとめたい意向だ。
これを受けて、松本真人委員(健康保険組合連合会理事)は「基本的には(有識者検討会の議論内容に)特別な配慮をあまり念頭に置かない形で議論を進める」との姿勢を示した。
また、長島公之委員(日医常任理事)は「改定内容そのものは中医協の所掌であり、(有識者検討会の議論の反映は)なされるものではない」とクギを刺した。
当初の厚労省のシナリオは違った。関係幹部によれば、有識者検討会として「10月中に中間年改定に向けた中間整理」をまとめる手筈だった。
だが、それは断念し、形を変えた格好で、24年度の制度改革を見据えた論点の取りまとめを行った。
そうした“縄張り”をめぐる水面下での攻防の結果、中間年改定について「有識者検討会にはモノを言わせない」体裁が取られた。
ただ、中医協に許された範囲は、もっぱら中間年改定に「どのルールを適用するか」というあたりまで。結局、改定を実施する場合の対象品目の範囲や規模といった重要な決定事項に関しては、予算編成時の政府の事務方折衝、または大臣折衝で決まる公算が大きい。つまり、中医協の「外」で決まるということだ。











-185x130.jpg)





【速記録】_ページ_01-のコピー.jpg)
【速記録】_ページ_01-のコピー.jpg)
【速記録】_ページ_01-のコピー.jpg)
_2023年8月2日の総会-1-190x190.jpg)

_2023年6月21日の中医協総会-190x190.jpg)








_2022年8月3日の中医協総会-190x190.jpg)















-190x190.jpg)


_20190807_中医協材料ヒアリング-300x300.jpg)