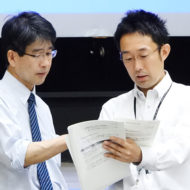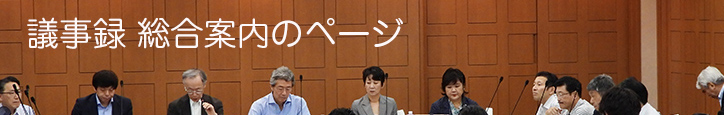さる9月14日に開かれた中央社会保険医療協議会の総会で、2号側委員の城守国斗委員(日本医師会常任理事)が退任の挨拶を述べ、“中医協軽視”の空気に不満を表明した。【鯉渕甫】
「医療政策色の強いテーマに関しては、中医協の外で一定の方向性が決められることは従来からあったが、近年その傾向が顕著になりつつある。中医協は財源配分を淡々と行う場にすぎず、医療政策や制度を議論する場ではないという中医協軽視とも取れる意見を言う方もいる」
中医協では、2号側委員7名のうち3名に日医代表委員が就任している。城守氏が述べた「中医協軽視」はすなわち“日医軽視”とも言える。メンツと権益を保持するにはメッセージを出すことが必須だったのだろう。
中医協の設置法である社会保険医療協議会法には、中医協の審議・建議事項に①療養の給付に要する費用の額②入院時食事療養費の額の勘案③保険外併用療養費の額の勘案④訪問看護療養費の額――などが記載され、政策策定や制度設計は記載されていない。
だが、それでも城守氏は反論した。
「中医協は、安易にその守備範囲を狭めてはいけない。診療報酬上の制度設計に関しては、やはり専門職が委員を務める中医協の場において主体的に議論をし、決定すべきではないだろうか」
同様の趣旨をもっと先鋭的に発言したのは、前日医会長の中川俊男氏だ。2021年11月17日の定例記者会見で財務省のスタンスを批判した。
「所管である財政の問題を超えて細かく医療の各論に踏み込んでくるのは、省としての守備範囲を超えており、現場の感覚と大きくずれている点もあり、容認できない指摘が多々ある。診療報酬は中医協で長年にわたり真摯に議論を積み重ねて現在に至る。財政審の主張は診療報酬の各論に踏み込みすぎであり、領空侵犯だ」
当時、この発言を知った財務省関係者は「診療報酬には膨大な国家予算を投入するのだから、財政当局として、政策立案や制度設計について今後もガンガン意見を述べていく」と歯牙にもかけなかった──。




-185x130.jpg)










【速記録】_ページ_01-のコピー.jpg)
【速記録】_ページ_01-のコピー.jpg)
【速記録】_ページ_01-のコピー.jpg)
_2023年8月2日の総会-1-190x190.jpg)

_2023年6月21日の中医協総会-190x190.jpg)








_2022年8月3日の中医協総会-190x190.jpg)















-190x190.jpg)


_20190807_中医協材料ヒアリング-300x300.jpg)